相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をする事です。
遺産分割協議をして、遺産を何ももらわなかったという事実は「相続放棄をした」事にはなりませんのでご注意ください。
このお手続きは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。
死亡から3か月以内ではありませんので、死亡の事実を知った時に既に3か月を経過していても慌てる事はありません。
相続放棄をする必要のない方が、うっかり相続放棄をしてしまうと取り返しのつかない事になりかねませんので、慎重に行う必要があります。
家庭裁判所へ提出する書類作成の代理人になれるのは司法書士のみです。
(弁護士を除く)
必要書類
申述人(相続放棄する方)ごとに必要書類が異なりますので該当する箇所をご確認ください。
※重複するものは1通で結構です。
※既に提出済みのものは添付不要です。
被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の子又は代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合(第一順位相続人)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人(孫・ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の父母・祖父母等の場合(第二順位相続人)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 祖父母が相続人の場合、父母の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合(第三順位相続人)
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 甥姪(代襲相続人)が相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
報酬
3か月以内 33,000円
3か月超え 66,000円~
※申述人が配偶者・子の場合です。
※申述人2人目から1万円引き
(同順位相続人に限る)
実費
- 申述人1人につき800円分の収入印紙
- 郵券
- 郵送費
手続きの流れ
予約・お問合せ
まずは、お電話・メール・LINEからご連絡をお願いします。
※ご事情があり、弊所までご来所が難しい場合はご相談ください。
※当日も空きがあれば予約可能ですが、必ずご予約をお願いします。

ご相談・お見積
お話を伺います。
ご持参いただいた資料を拝見し見積書を作成・お手続きの流れ等をご説明します。
※ご自宅に持ち帰りご検討頂いても結構です。

お申込・書類預り
見積等にご納得いただけましたら、申し込み手続きをします。

業務開始
お預り書類を確認し、不足がある場合は戸籍等を収集します。
必要書類が全て整いましたら書類を作成します。
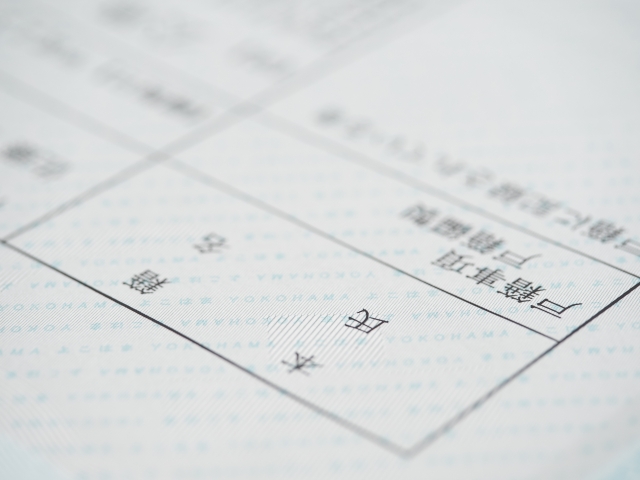
支払・納品(終了)
(郵送の場合)
お振込を確認後、書類一式をご自宅へ発送します。
お手元に届きましたら、申述書に「押印」していただき、同封したレターパック(裁判所宛名・差出人宛名付き)に封入し、ご自身でポストへ投函して頂きます。
(ご来所の場合)
お支払いをお願いします。
申述書に「押印」をしていただき、お控えをお渡しします。
弊所にて発送まで承ります。

家庭裁判所にて受付~受理
家庭裁判所に受付がされてから2週間程で「照会書」が届きますので回答書を返送してください。
照会書の代わりに電話が入る事や、照会なしで受理される事もあります。
その後、受理されると2週間程で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書は再発行ができませんので大切に保管してください。
※「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、ご自身で申請手続きが必要です。

よくあるご質問
-
事務所には何回行くことになりますか?
-
基本的に1回で結構です。
-
住民票や戸籍等の取得をお願いできますか?
-
はい、承っております。
-
事務所によって報酬は違いますか?
-
はい、異なります。
-
費用の支払いはいつですか?
-
書類提出前にお支払いいただきます。